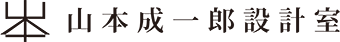5月23日、私が舎弟を務める内田祥士先生(建築家・東洋大学教授)の講演を拝聴してきました。
タイトルは「電柱・電線は、何故、埋めたくなるのか」。
電柱・電線の細部の納まり(継手や仕口)そのものは、ひとつひとつが規格化され整然としているにもかかわらず、それらが集積すると(内田先生言うところの)「壮麗」な様相を呈します。
要するに、美しくない、という事であります。
そのような美醜の問題をはらむ一方で、電柱・電線は、機能的には全く破綻する事無く日々粛々と私たちの生活を支え続けています。
こんな健気な彼等に、一体どんな罪があろうと言うのでしょうか?

その「壮麗」な有様は、個人であれ組織であれ、各々の欲望が制御される事無くありのままに表出されてしまった現代日本における都市の姿と、酷似している(あるいは相似形)ではありませんか。
現代文明や市場社会の在り方について深く考えさせられるお話でございました。
アニキ、一生付いていきますっ! ……たぶん(笑)
(写真は当日の配布資料から頂戴しました)
追記
同日拝聴した仲綾子先生の「建築写真には、何故、人が居ないのか」及び高橋良至先生の「鉄道時刻表は、何故、読み物ではないのか」も実に興味深いお話で、誠に濃密で有意義な時間を過ごさせていただきました。
平成27(2015)年7月4日追記
浅古陽介先生が撮影された上記講演の動画が公開されました。是非御覧ください。
内田祥士研究室「電柱・電線はなぜ埋めたくなるのか」1/6~6/6